『価値づくり』の研究開発マネジメント 第366回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(213): KETICモデル- C:Curiosity(好奇心)(3)
好奇心は何によって生まれるのか(3)
(2025年10月20日)
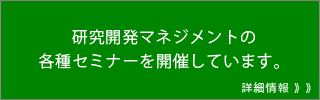 |
今回も、前回に引き続き「好奇心は何によって生まれるのか?」の議論を続けていきます。
●好奇心は何によって生まれるか?(その1):好奇心の結果が自分にとって広い意味で価値を生み出すこと(その3)
〇好奇心における「価値」の意味:「価値」の認識はどこから生まれるか?
そもそも人間にとって「価値」を感じさせる要素には、どのようなものがあるのでしょうか?
人間の行動や欲求を生み出す背景に、自分もしくは自分達にとって益のあるもの、すなわち自分達にとっての「価値」があると思います。そのような「価値」をもとめての人間の行動や欲求を生み出すドライバーとして、ドーパミンなどの脳内の神経伝達物質の存在があるようです。脳内の神経伝達物資と言うと、好奇心の議論をするには過度に細部に入り込んでいるようにも思えるかもしれませんが、脳内の神経伝達物資の議論は、好奇心が何によってもたらされるかの根本的な原因を提示してくれるもので、極めて重要な議論と考えますので、今回からこの議論をしていきたいと思います。
〇好奇心の根本のドライバー:脳内の神経伝達物質
好奇心に関連する脳内の神経伝達物質には、ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリン、オキシトシンといった複数の物質があります。当然のごとく、それぞれの物質は人間の心理全体へ異なる効果を生み出していますので、これら神経伝達物質ごとにどう好奇心生成に関与しているのかを議論してみたいと思います。
〇脳内の神経伝達物質(その1):ドーパミン
代表的な脳内の神経伝達物質が、ドーパミンです。ドーパミンはこれまで快楽物質と呼ばれ、脳内で快楽の感覚を生み出す物質と理解されてきましたが、最新の研究ではそれは誤りであることがわかっています。ドーパミンは、現在では「動機付け」、「学習」、そして「動機付け」→「学習」→「動機付け」の循環といった機能を直接的に生み出す物質として理解されています。このドーパミンが、これら機能をどう生み出すのかを議論したいと思います。
-第1ステップ:最初の「動機付け」
まず最初に、ドーパミンは「これをすれば良いことが起こるかも」と予想や期待した瞬間に分泌されます。このドーパミンの脳内での分泌により、脳はその行動を「やってみたい」「試したい」と感じ、実際の行動が促されます。ですので、少なくとも最初においては、「これをすれば良いことが起こるかも」と、自ら予想・期待をしなければなりません。すなわち、この第1ステップである最初の「動機付け」は、所与のものでなければなりません。
「なんだ、好奇心とはそもそも「これをすれば良いことが起こるかも」と思えることそのものであるのに、ドーパミンはここに関係しないんだ」と、がっかりするかもしれません。しかし、これはまた後に詳しく説明をしますが、今ここで議論している最初の「動機付け」の結果、後の第2ステップである「学習」がなされ、そしてその「学習」結果がさらなる次の「動機付け」を促進するという循環の仕組みが脳の中に作られることになります。
この議論は次回も続けていきます。
(浪江一公)