『価値づくり』の研究開発マネジメント 第365回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(212): KETICモデル- C:Curiosity(好奇心)(2)
好奇心は何によって生まれるのか(2)
(2025年10月6日)
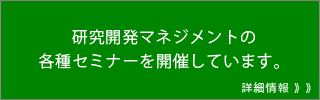 |
前回からKETICモデルの最後の項目であるC:Curiosity(好奇心)の議論を始めました。前回に引き続き今回も「好奇心は何によって生まれるか?(その1)」の議論を続けていきたいと思います。
●好奇心は何によって生まれるか?(その1):好奇心の結果が自分にとって広い意味で価値を生み出すこと(続き)
〇「自分にとって広い意味で」の意味:実現する価値は必ずしも自分が直接享受するものに限定しない(続き)前回の議論で、自分が認識し感じる価値は、自分にとっての直接的な価値だけではない。たとえば、周りの人達、社会、そして地球環境などにとっての価値も、最終的には自分にとっての価値として認識し、感じることができるという議論をしました。
よくよく考えてみると、「自分にとっての直接的な価値だけではない」価値とは、以下2つの種類があるように思えます。これら2つは似たように思えるかもしれませんが、私自身の感覚からは明らかに異なるものです。
-1:他者に貢献することで生まれる充実感による価値
他人を助け感謝される、すなわち他人から「自分は価値がある」と認められるとうれしいと感じる価値です。逆に他人から「自分は価値がない」と言われるほど傷つき、腹が立つことはありません。したがって、他人から「自分は価値がある」と認められることは、自分が普段認識している以上に大きなことのように思えます。ですので、他者への貢献により感謝されることによる充実感による価値には、極めて大きなものがあるようです。
ここで重要なことが、実際には他者に貢献できていなくても、そもそもそれが他者に貢献するようなものでなくても、他者に貢献する活動をしていると本人が「信じる」ことができれば、それは自分にとって価値があるという点です。
私の知り合いに、環境への影響からマイ箸をいつも持ち歩いている女性がいました。残念ながらマイ箸を使うことによる自然環境へのポジティブな影響はまったくありません。逆に、森を良い状態にするために発生する間伐材は(この場合割り箸として)、どんどん活用した方が実は自然環境には良いのです。でも本人は、マイ箸を使うことで割り箸の使用を減らすことができ、環境に良い影響を与えると信じていて、大変大事で価値があると考えていて、この活動を続けているのです。
-2:他者を同一化・自己拡張することで生まれる満足感による価値
人間は、自分にとって直接的そして間接的にも全く益がなくても、単純に他者がうれしいと自分もうれしいと感じるということがあります。この点は心理学でも、東西の哲学でも、また脳科学的にも証明されているようです。
心理学の言葉に感情的共感というものがあり、人間は相手の感情を自分自身のものとして経験することができるということがあります。仏教の世界では、他者の善行や幸福を自分のことのように喜ぶ態度を「随喜」と呼んでいます。西洋哲学ではアダム・スミスが『道徳感情論』の中で、「人は他者の喜びを共に喜び、悲しみを共に悲しむ能力を持つ」と述べました。また脳科学においては、人間は相手の表情や声のトーンを無意識に模倣し、その結果、相手の喜びの感情が自分の身体・脳の中に「コピー」され、同じように嬉しくなることがわかっています。
我々は普段はあまり認識しないのですが、これら価値を広く認識することにつながる人間の利他の心理は、このように二重に強く心の中にインプリントされていて、きっと人類の繁栄の重要要件として存在するのでしょう。
(浪江一公)