『価値づくり』の研究開発マネジメント 第364回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(211): KETICモデル- C:Curiosity(好奇心)(1)
好奇心は何によって生まれるのか(1)
(2025年9月22日)
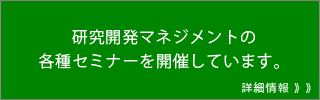 |
実はここにきて、前回までずっと152回をも費やして議論をしてきたイノベーションを起こすためのKETICモデルにおける「T:Thought(思考)」ですが、良く考えてみるとMECEの議論の無限ループの中で、以前議論した内容を蒸し返して議論をしていると思い当たりました。また、本メルマガを読んでいる方々も、飽きてしまっているのではないかと思います。
そこで、「T:思考」の議論はまだ完結はしていませんが、またまだKETICモデルの4つ目のI:Intention(意思)の議論はしていませんが、今回からKETICモデルの最後の項目であるC:Curiosity(好奇心)に進み、そこでの議論をしたいと思います。
●好奇心は何によって生まれるか?(その1):好奇心の結果が自分にとって広い意味で価値を生み出すこと
まず一つ目に、好奇心の先に最終的に「自分にとって広い意味で価値」があるとその価値を実現するために好奇心が生まれるということです。ここで重要なことが「自分にとって広い意味で」と「価値」の2つの点です。まず2つの目の「良いこと」について考えてみたいと思います。
〇「価値」の意味:全ての人間の心理や行動には目的がある、すなわちそこに本人にとっての価値がある
私は全ての人間の心理や行動には、かならずそこには目的があると思います。
「目的もなく歩き回る」などの表現がありますが、歩き回る目的には本人が明確に意識していなくても、たとえば「目的もなく歩き回る」ことで、もやもやした考えを形にするや、悲しみを癒すなど、目的があるはずです。また本人が意図せず行う貧乏ゆすりも、そこには、筋肉の緊張を和らげるなど目的があります。
そして人間の心理や行動に目的があるのであれば、その先にはその目的を達成することで価値が生まれるということです。価値は人間の心理や行動のドライバーです。
たとえば、昆虫に好奇心をもって、昆虫採集をする人がいます。その人にとっての昆虫採集をする目的はなんでしょうか。私自身には特に虫には関心がないので、完全に昆虫採集者の心理を理解している訳ではありませんが、昆虫という小さなかわいい生き物に触れることでの癒しを得ることや、希少な昆虫を手に入れる達成感を獲得するなど、本人にとってかならずそこには自分にとっての目的があります。そして、その目的を実現することには本人にとって価値があります。
〇「自分にとって広い意味で」の意味:実現する価値は必ずしも自分が直接享受するものに限定しない
次に1つ目の「自分にとって広い意味で」についてです。
その心理や行動が自分ではない第三者や社会や環境にとって価値がある、ということもあると思います。友達を助けるや地球の温暖化や社会の貧困化抑制に貢献するなどです。しかし、それらは一見利他的な行動や心理ではあっても、それは最終的にはそれらを通じて、自分自身の充実感という自分自身にとっての価値につながるものであることは明らかです。人間は、そういうことにも好奇心を持ちます。
〇好奇心の対象は本人次第であるゆえ、好奇心の対象は無限
人間の欲望には、70の種類があるとの心理学者の研究があります。言い換えると価値を認識する分野は人間に「共通的に」あるということです。しかし、個人レベルではそれら70の欲望を常に認識し、それに基づきものを考えたり、行動したりするわけではありません。その時々の心理状態や置かれた環境、またその個人のそれまでの経験やそれまで得た知識、そして遺伝的な特徴によって大きく変わってきます。そのため、何に価値を認識するかは本人次第という面が多分にあり、したがって好奇心の対象も多様ですし、そのため好奇心の対象の広がりはほぼ無限といって良いでしょう。
(浪江一公)