『価値づくり』の研究開発マネジメント 第363回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(210): KETICモデル-思考(152)
「発想のフレームワーク(87):重要な発想法としての隣接可能性とは(15):隣接可能性促進法(13)」
(2025年9月8日)
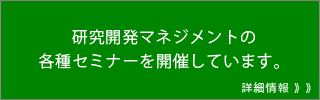 |
ここまで重要な発想法としての隣接可能性の思考パターンの内、MECEの思考パターンとして、5つを説明してきました。しかし、ここで重要な点として、これら5つがそれこそ、そもそも思考のパターンとしてMECE(だぶりなく、もれなく)なのか?というものがあります。さらに、これら5つの思考パターンを構成する、サブ思考パターンとしてどのようなものがあるか?は、物事を発想する上でもおおいに参考になります。今回も、その点について考えてみたいと思います。
●前回の議論のまとめ
前回までに5つの思考パターンの内<並列>について議論をし、そのサブ思考パターンとして以下の暫定的結論を得ました。
-<並列>の中であげられた項目間に関係性「あり」
更にそれらは、3つの思考パターンがある。
・対立
・協調
・中立
-<並列>の中であげられた項目間に関係性「なし」
更にそれらは、2つの思考パターンがある。
・類似
・類似以外のもの
●「類似以外のもの」について:類似以外の概念に何があるか?
チャットGPTに、「<並列>の中であげられた項目間に関係性「なし」」にはどのような項目があるかを、聞いてみました。その結果、「類似」を含め、この3つが示されました。
・同一:すべての属性が一致
・相違:共通する属性がない
・類似:共通部分があるが、完全には一致しない
以下順番に、議論をしたいと思います。
〇同一
「同一」、すなわち全ての属性が一致するのであれば、別の項目を立てる必要はありませんので、サブ思考パターンとしては不適ということになります。つまりAからB(すなわちAでないものに何があるかを考えてみて、Bが発想された)というアイデアが出てきた場合、AとBの全ての属性が一致するのであれば、Bは不要ということになります。つまり、この場合BはAの言い換えにすぎないということです。
〇相違
「相違」、すなわち「共通する属性がない」ということであれば、<並列>の中には出てきようもありませんので、サブ思考パターンとしては、これも不適ということになります。
つまり、<並列>のいずれの思考パターンで得られるアイデアも、いずれもその思考のパスは、共通する「属性」によってつながっています。たとえば、発想の出発点として「バナナ」があり、そこから<並列>の発想をし、「そう(つまりバナナ)でないもの」を考えてみると、「リンゴ」が出てきます。「そうでないもの」と言っても、同じ上位概念の「果物」の構成要素ですので、「バナナ」と「リンゴ」は必ず「果物」である属性を共有しています。
〇類似
「類似」は、「共通部分があるが、完全には一致しない」というものです。そう考えると、<並列>の思考パターンで発想されるものは、必然的に共通の属性があるのですから、よくよく考えてみると、冒頭で「類似」は「サブ」思考パターンと説明しましたが、それはまったくの誤りで、「サブ」どころか、<並列>の思考パターンを包括するメタ的な概念ということになります。
●この議論の結論
冒頭で、
<並列>の中であげられた項目間に関係性「なし」
・類似
・類似以外のもの(※:この項目については、別の所でさらに議論が必要)
という議論をしましたが、結論としては、「類似以外のもの」はなく、「類似」だけであるということです。また、<並列>の思考パターンから出てくるアイデアは、必ず「類似」しているということです。そうすると、冒頭であげた「●前回の議論のまとめ」の内容を、もう少し整理する必要があるようです。この議論は次回したいと思います。
(浪江一公)