『価値づくり』の研究開発マネジメント 第362回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(209): KETICモデル-思考(151)
「発想のフレームワーク(86):隣接可能性とは(14):隣接可能性促進法(12)」
(2025年8月25日)
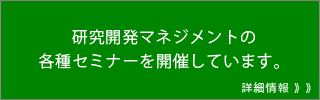 |
ここまでMECEの思考パターンとして、5つを説明してきました。しかし、ここで重要な点として、これら5つがそれこそ、そもそも思考のパターンとしてMECE(だぶりなく、もれなく)なのか?というものがあります。前回に引き続き、その点について考えてみたいと思います。前回は「類似」を議論しました。今回は、「対立」について議論したいと思います。
●対立
そもそも対立の定義はなんであるかを、チャットGPTに聞いてみました。
対立とは、複数の主体(個人・集団・組織・国家など)の間で、利害・価値観・意見・欲求・目標が両立せず、緊張や摩擦を生じている状態を指します。
ここは「複数の主体の間」とありますが、これら主体は同じレベルで、かつお互いに相互排他的(だぶりなく)の関係にあると考えられますので、5つの思考パターンの中の「横展開<並列>」、すなわち「そうでないもの」の概念の中に納まる一つの概念と考えられます。ですので、「対立」は「横展開<並列>」の中で、その構成要素間で「利害・価値観・意見・欲求・目標が両立せず、緊張や摩擦を生じている」場合を言い、前回で使った言葉をここでも使うと、5つの「メイン」思考パターンの体系の中に納まる「サブ」思考パターンと理解できます。
そうすると「横展開<並列>」の中の「サブ」思考パターンとして、「対立」以外のものとして、どのような思考パターンがあるか考えてみたくなります。
そこで「対立」ではない、「横展開<並列>」の思考パターンに何があるのかを考えてみると、「対立」の対局に位置付けられる「協調」があります。そうすると、次に「対立」でも「協調」でもない、お互いに何の影響を及ぼさない状況、すなわち「共存」が考えられます。つまり、「対立」、「協調」、「共存」は、構成要素間の関係性をそれぞれネガティブ、ポジティブ、ニュートラルにより定義した「サブ」思考パターンというものです。
そうすると次にさらに、構成要素間の関係性の概念に別のものはないのか?さらにそもそも、構成要素間の関係性ではない別の定義があるのか?という質問が出てきます。以下にこの2つについて考えてみたいと思います。
〇構成要素間の関係性の概念に別のものはないのか?
<並列>の中に、ネガティブ、ポジティブ、ニュートラルの関係性以外の「関係性」があるか、という議論です。厳密にいうと、
・これらの強度(特にネガティブ、ポジティブについて)により、さらに分割
・これら3つのうち、ニュートラルと他2つの中間に位置する物(ネガティブとニュートラルの間など)
・時と共にこれら関係性を行き来するもの(ある時はネガティブ、ある時はニュートラルなど)があります。しかし、因数分解するとこの3つになるので、基本はこのネガティブ、ポジティブ、ニュートラルの3つと考えて良いように思えます。
〇構成要素間の関係性ではない別の定義があるのか?
これは、<並列>の中にネガティブ、ポジティブ、ニュートラルなどの「関係性」ではない別の分類があるか、という議論です。この点について考えてみると、「関係性がある」に対して「関係性がない」というものがあります。「関係性がない」とは、<並列>の中にあがった項目が、そのグループ間では関係性のないなんらかのグループから構成されるというものです。
そう考えてみると、前回議論した「類似」は、この「関係性のない」思考パターンに属すものと考えることができます。
以上前回の「類似」の議論を含め、ここまでの議論を整理すると以下のようになります。
<並列>の中であげられた項目間に関係性「あり」
更にそれらは、3つの思考パターンがある。
・対立
・協調
・中立
<並列>の中であげられた項目間に関係性「なし」
・類似
・類似以外のもの(※:この項目については、別の所でさらに議論が必要)
次回もこの議論を続けていきたいと思います。
(浪江一公)