『価値づくり』の研究開発マネジメント 第361回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(208): KETICモデル-思考(150)
「発想のフレームワーク(85):隣接可能性とは(13):隣接可能性促進法(11)」
(2025年8月4日)
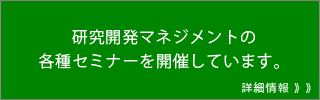 |
今回も引き続き隣接可能性の促進法として、MECE(だぶりなく、もれなく)の議論をしていきたいと思います。
ここまでMECEの思考パターンとして、5つを説明してきました。しかし、ここで重要な点として、これら5つがそれこそ、そもそも思考のパターンとしてMECE(だぶりなく、もれなく)なのか?というものがあります。今回から、その点について考えてみたいと思います。
●この5つの思考パターンは、それ自体網羅性(「もれなく」)があるのか?
〇「もれなく」かどうかを確認する方法としての生成AI
そもそも、「もれなく」かどうかを確認する方法はあるのか?という問題があります。私も含めて、人間は知らないことは議論ができません。残念なことに、私の知らないことは膨大に、いや無限にあります。そこで、ネット上に存在する知識を広くベースとしているチャットGPTに聞いてみました。まさに生成AIは、この目的にピッタリです。チャットGPTによると、他に、類似、対立、順序・時間的関係、目的と手段、空間的・位置的関係があるとのことです。
※: MECEの「だぶりなく」の部分は、その情報の間に「だぶり」があるかないかは、その目の前にあるそれら情報について考えてみることで、だぶりがあるかどうかを判断し、もしだぶりがあれば目の前にある情報に基づき整理することが可能と思います(つまり「もれなく」の様には欠けている情報はない)。
それでは、ひとつひとつ、これらが追加すべき新な思考パターンとなるのか、について議論をしていきたいと思います。
〇類似
まず最初に、「類似」から議論をしたいと思います。
すでにリンゴが発想されていれば、リンゴのように球形ではないが、植物に生える甘い味がするものとしてバナナがあるという「類似」なものを考えるという発想はあります。この場合、バナナは植物学的には果物ですので、リンゴの「上位概念<包括>」(5つの思考パターンの1つ)の果物(X)に属する他のものすなわち「横展開<並列>」(これも5つの思考パターンの1つ)のものとしてバナナを位置付けることができます。
また、リンゴ(A)が発想されていれば、リンゴの「上位概念(包括)」の果物(X)ではないかもしれないが、「類似」したものとしてニンジンを発想することができます。ニンジンが発想できたとすると、ニンジンは植物学的には果物ではないな。なんだろう。野菜(Y)だ!と果物(X)からの「横展開<並列>」として野菜(Y)を発想し、その野菜(Y)中の「下方展開<分割>」の構成要素として、ニンジンを位置づけ「整理」することができます。
したがって、基本的にこの「類似」の思考は、ここまで議論した5つの思考パターンの体系に納めて考えることができます。
しかし、ここでは「整理」することが目的ではなく、「思考」を促すための「思考」パターンを議論しているのですから、「類似」は確かに、新しい思考を促す思考パターンとして(「横展開<並列>」の基本的な問い掛けである「同じもの」に加えて)、有効なものです。そこで5つの「メイン」思考パターンの体系の中に納まる「サブ」思考パターンとして、位置付けるのが適正ではないかと思います。
そうすると、「同じ」や「類似」以外の「サブ」思考パターンはないのか?という疑問が湧いてきます。この議論は、この後に続くチャットGPTが提示した対立、順序・時間的関係、目的と手段、空間的・位置的関係の議論を終えたあとに、まとめて議論をしたいと思います。
(浪江一公)