『価値づくり』の研究開発マネジメント 第360回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(207): KETICモデル-思考(149)
「発想のフレームワーク(84):隣接可能性とは(12):隣接可能性促進法(10)」
(2025年7月22日)
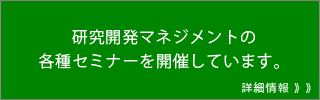 |
今回も、隣接可能性を促進する方法として、MECEについて議論をしていきたいと思います。今回は3つの展開の内、最後の横展開<並列>について議論をします。
●横展開<並列>
〇横展開とは
横展開とは、
(X)
↓
A→B
のように、Aから同じグループに属す同じレベルの他のもの(B)、すなわちAではないものとして横に展開して発想するというものです。たとえば、果物(X)に属するものでりんご(A)が最初に思いついた(ちなみにこれは下方展開<分割>の発想です)。それでは、リンゴ(A)でないものにはなにがあるか?みかん(B)がある、という発想です。「すでにグループ(この例では果物)が特定されていて」、同じグループの他のものを発想しますので、下方展開にあった<結果>や<分割>、上方展開の<原因>や<包括>のように2つの種類はありません。
〇「すでにグループ(この例では果物)が特定されていて」について
ここで、上で「すでにグループ(この例では果物)が特定されていて」といいましたが、実際には明確にクリアにそのグループが特定されていなくても、すなわち「なんとなく、ぼんやり」わかっているだけでも、この横展開は可能です。果物(X)という概念を明確に認識していなくても、単に、リンゴ(A)以外に何があるか?と問いかけて、みかん(B)があるという発想は実は可能です。その際、実際には果物(X)というのが頭のなかでぼんやり、もしくは無意識に理解されているので、みかん(B)という発想は現実には可能となります。
〇横展開と上方展開の関係について
ここで、「次のステップ」として重要な発想の方向が、ぼんやりしか理解していない、もしくは無意識に理解されている果物(X)(上方展開先)を明確に認識することです。なぜかというと、上方展開で発想した果物(X)が発想できれば、すなわちそうかリンゴ(A)やみかん(B)の上位概念が果物(X)なんだということがわかば、今度は明確に果物(X)を認識したうえで、他にはどのような果物があるのか?という問い掛けにつなげることができ、バナナがあるという発想をさらに拡大することをより容易にすることができます。
ここでの重要なポイントが、リンゴ(A)とみかん(B)という2つの発想済のアイデアがあれば、リンゴ(A)という1つの発想しかない場合に比べ、リンゴ(A)とみかん(B)の共通項は何かという追加的な思考の補助線があるので、果物(X)を発想することは各段に容易になります。
〇人間は脳という蔵の中に認識している以上の膨大な情報を持つこの議論からわかることは、人間は本人が明確に意識していることに比べ、遥かの多くの情報を頭の中に無意識に蓄積していることです。私は人間の脳を、本人は認識していないが沢山の宝を収蔵している蔵になぞらえています。
ただし、頭の中の膨大な情報のほとんどは未加工で、すなわちそれら情報の関連性が整理されていないのです。そこでMECEの思考法を活用し、それらを整理すると自分が認識していなかった発想、すなわちイノベーションを起こすことができるということです。
(浪江一公)