『価値づくり』の研究開発マネジメント 第359回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(206): KETICモデル-思考(148)
「発想のフレームワーク(83):隣接可能性とは(11):隣接可能性促進法(9)」
(2025年7月7日)
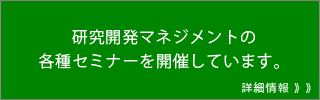 |
今回も、前回に引き続き隣接可能性を促進する方法として、MECEについて議論をしていきたいと思います。前回は、下方展開を議論しましたので、今回は上方展開について議論をします。
●上方展開
〇上方展開とは
上方展開とは、
X
↑
A
のように、Aを出発点に、図のように図の上方にXを発想するというものです。上方展開の思考パターンにも2つあります。<原因>と<包括>です。
<原因>は下方展開で議論した<結果>の逆で、Aという結果を生み出している原因は何かを考え、その原因であるXを記述するものです。たとえば、「海面上昇(A)の原因は何だろう?」と考えてみて、「そうだ、地球温暖化(X)だ!」と発想する関係です。
<包括>下方展開で議論した<分割>の逆で、Aを包括・包含するより上位の概念は何かを考えて、記述するというものです。たとえば、地球温暖化(A)を包含・包括する上位概念は何かを考え、異常気象(X)であると発想するものです。
〇なぜ上方展開がイノベーションにおいて重要なのか?なぜ原因にしても包括にしても、上方に展開する必要があるのかというと、上方に展開すれば、また下方展開の2つの思考法(すなわち結果と分割)により、下に展開することができ(下の図で、X→B、X→Cのように)、発想が広がるからです。
X
↑ ↓ ↓
A B C
たとえば、上の<原因>の例でいえば、地球温暖化(X)がもたらすものに、海面上昇以外に何があるか?そうだ、温帯地域の熱帯化(B)もあるという発想です。下方展開の<分割>の発想をするというものもあります。たとえば、海洋地域の温暖化(α)、陸上の温暖化(β)などです。
〇原因、包括、結果、分割の発想の切り口は複数ある
ここまでの議論ですでに気が付かれた方もいると思いますが、原因、包括、結果、分割の発想の切り口は複数あります。
たとえば、<原因>では海面上昇(A)の原因を考える場合、熱源の吸収に関する複数の原因(切り口1)と放射阻害による複数の原因(切り口2)があるかもしれません。ここで「複数」と言っている意味は、熱源の吸収という切り口で考えてみると、太陽光による熱、人間の営みから発生する熱、地球のマグマによる熱などの複数の原因に展開できるという意味です。
〇発想の切り口自体もMECEで網羅的に数多く考えてみる
発想の切り口も多数あれば、発想が大きく広がります。そこで、ここで重要なのが、切り口自体もMECE(だぶりなく、もれなく)で考えることで、発想の切り口も数多くまさに発想することができます。
(浪江一公)