『価値づくり』の研究開発マネジメント 第358回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(205): KETICモデル-思考(147)
「発想のフレームワーク(82):隣接可能性とは(10):隣接可能性促進法(8)」
(2025年6月23日)
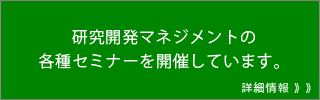 |
今回も、前回に引き続き隣接可能性を促進する方法として、MECEについて議論をしていきたいと思います。
●MECEの5つの思考パターン
前回のメルマガの記事の中で、5つの思考パターンがあるとお話をしました。まずは、5つの思考パターンの内、2つのパターンに対応する下方展開から議論をします。
〇下方展開
下方展開とは、
X
↓ ↓ ↓
A B C ・・・・
と最初に発想したXを出発点に、図の上で下に向かって(下方)にA、B、C・・・を(発想し)記述するという意味です。この下方展開の思考パターンには、2つあります。<結果>と<分割>です。すなわち、この図の例でいうと、XとA、B、C・・・の関係に、<結果>と<分割>があります。
<結果>は、Xを原因にA、B、C・・・という結果を生み出すというものです。たとえば、地球の温暖化(X)を原因に、海面上昇(A)、温帯地域の熱帯化(B)、大地の乾燥(C)・・・という互いにだぶりのない結果を引き起こすという関係です。つまり、Xを原因として、どのような結果が生まれるのかを考えるということです。
<分割>は、XはA、B、C・・・に分割されるというものです。たとえば、がん(X)には、大腸がん(A)、肝臓がん(C)、膵臓がん(C)・・・というお互いにだぶりのない部分に分割して発想・記述するものです。
Xはすでに発想済で、そこにあるのであれば、Xを原因とすると、Xという原因はどのような結果を生み出すのだろうか?(結果) また、Xはどのようなものから構成されるのだろうか?(分割)という思考をすることは、難しくありません。まさに隣接可能性では、Xから「隣接する」結果や構成する部分を想定することは、何も無いところから発想するよりもはるかに容易であるということです。
これはまた後に「横展開<並列>」の中で議論しますが、MECEでは「だぶりなく、もれなく」思考するものなので、A、B、C・・・は、だぶりなく、そしてもれなく、発想・記述されている必要があります。「もれなく」ですので、XからAが発想されたら、A以外のものはないのか?も同時に考える必要があります。また「だぶりなく」ですから、発想した(正確にはこれから発想「する」)A、B、C・・・はお互いにだぶりがないものである必要があります。
この点(だぶりなく、もれなく)は発想を促進する上で重要で、A、B、C・・・間に「だぶり」があると、「もれがある」のか?どうかがわからなくなってしまい、他にもっと発想する余地があるのに発想が中途半端なままで終わってしまうということになってしまいます。
以前に私のセミナーでMECEに関し、この2種類(<結果>と<分割>、そして後に説明するそのまったくの逆である<原因>と<包括>(後に上方のところで議論をします)があると説明をしたところ、参加者の一人である会社の知財担当課長をされておられる方からアドバイスをいただきました。この方のアドバイスは、下方や上方に2種類の異質の思考パターンがあるのは複雑で、どちらかに絞るのが良いというものでした。たしかに、この2つの思考パターンは異質であるのですが、MECEは新しいアイデアを見つけるためのツールですので、多少の複雑性は甘受し、この2つの思考パターンをきちんと明示するのが良いと考えています。
(浪江一公)