『価値づくり』の研究開発マネジメント 第357回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(204): KETICモデル-思考(146)
「発想のフレームワーク(81):隣接可能性とは(9):隣接可能性促進法(7)」
(2025年6月9日)
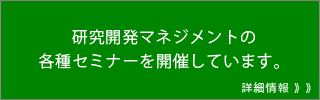 |
今回からは、隣接可能性を促進する方法として、MECEについて議論をしていきたいと思います。
●MECE(だぶりなく、もれなく)
MECE(ミーシー)は、一般的に思考の整理法として利用されるものです。さまざまな複雑な物事の関連性をだぶりなく、もれなくの構造で、通常ピラミッド構造に整理する手法です。わたしは、40年近く前に新人コンサルタントになった時、経営コンサルタントとしてこのMECEを勉強させられました。そしてその後経営コンサルタントの仕事の中で、クライエントの経営課題などの整理に、良くこのMECEを使いました。
しかしそこでは課題の整理法として利用してきたのですが、いつしかむしろ発想法として主に利用するようになりました。それは、「すでにわかっている」複数の物事をピラミッド構造に整理する中で、MECEを使うと「まだわかっていない」ことを想定することができることに気が付いたからです。
たとえば、原因のXと結果のAが他のなんらかの分析からわかったとします。X→Aという関係をMECEの図に表すと(MECEの図では、実際にはXが上に、Aがその下にぶらさがるのですが)、ちょっとまてよ、Xが生み出すのはAだけなのか?という疑問が生まれてきます。MECEは「だぶりなく」・「もれなく」なので、MECEの図の中にはXが生み出す全ての結果を「だぶりなく」の形で「もれなく」記述しなければなりません。そこで、Xという原因がわかっているのですから、Xが生み出すA以外の(すなわち「だぶりのない」)BやCを想定することは、それほど難しくはありません。
ここが、まさに今議論している隣接可能性の部分です。原因Xの存在にすでに気が付いているので、まさに「隣接」するBやCを想定することは、それほど難しくはないのです。
そしてMECEの思考の連鎖はそこで終わりません。AそしてBやCを抽出することができたので、そこからA、B、Cなどが生み出す結果(a1 a2 a3・・・ b1 b2 b3・・・ c1 c2 c3・・・)には、どのようなものがあるのか?という思考につながっていきます。ここでもA、B、Cが分かっているのですから、そのような思考は難しくはありません。
〇MECEのメリット
このようにMECEを使うと、一つの発想の基(上の例で言うとX→A)から、他の連想を効率的に隣接可能性を用いて網羅的に引き出すことができることです。イメージでいうと、一つの発想(!)ができると、あっと言う間に(現実的にはあっと言う間ではありませんが)、波紋が広がるように、以下のようにそれこそ数多くの他の事象がその関連性を持ってピラミッド状に広がっていくというものです。
X
↓
A B C
↓
a1 a2 a3・・・ b1 b2 b3・・・ c1 c2 c3・・・
〇MECEの5つの思考パターン
上では原因と結果でMECEを説明しましたが、実際にはMECEで発想する思考には5つのパターンがあります。それは以下の5つです。
-下方展開(その1)<結果>
-下方展開(その2)<分割>
-上方展開(その1)<包括>
-上方展開(その2)<原因>
-横展開<並列>
次回もこの議論を続けていきたいと思います。
(浪江一公)