『価値づくり』の研究開発マネジメント 第352回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(199): KETICモデル-思考(141)
「発想のフレームワーク(76):隣接可能性とは(4):隣接可能性促進法(2)」
(2025年3月17日)
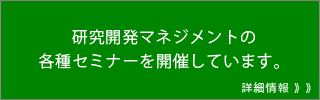 |
今回は、隣接可能性促進法の1つとして前回に触れた、4つの「意図的に隣接可能性を促進する方法」の1つ目として「既存のニューロンに蓄積された個別の情報を出発点に連想を促す」方法について、考えてみたいと思います。
●既存のニューロンに蓄積された個別の情報を出発点に連想を促す
これは、自分の脳内に蓄積済のひとつの情報から、同じように脳内に蓄積済の他の情報を、シナプスによりつなげ、関連付けることにより連想を促すというものです。そのための複数のツールについて、一つ一つ議論をしていきたいと思います。
〇マインドマップ
-図示(視覚情報)の効果
イノベーションやそのための隣接可能性を促進するための方法として、考えを図で表すという視覚的効果は、想像以上に大きなものがあると思います。
つい最近、目の前に視覚情報として示す図示と、単に頭の中で想像すること、との差の大きさを実感する経験をしました。私はこの歳になって数年前から趣味でピアノを始め、毎日練習をしていますが、つい最近ド→ソ→ミ→ド(上のド)という単純な指の動かし方の練習をしました。鍵盤を見ながら、という現物の視覚情報が与えられている状況であれば、もちろん難なくできます。しかし、鍵盤を見ないで弾こうとするとこれが大変難しい。鍵盤の配置は日々見慣れている筈なのに、頭の中ではドレミあたりまでの配置はそれなりに明確に映像情報として記憶しているので、それを頭の中でイメージしながら鍵盤を見ずに鍵盤を指でなぞることはできるのですが、ファソラシドあたりの映像情報は頭の中では霧に包まれているようで、うまく弾けません。
鍵盤の配置は、全く複雑なものではありませんし、またそれを何年間も毎日見てきているのです。しかし、それが頭の中にきちんと整理されて記憶されていないのです。
目の前に提示された視覚情報(鍵盤の配列など)は、頭の中に記憶されている情報に比べ、当たり前ですが遥かに細部まで明確であるということが言えると思います。
-マインドマップとは
連想を構造化して視覚的に図示するに有用なツールが、マインドマップです。マインドマップは、出発点となる情報、概念、アイデアなどを図の真ん中に記述し、そこから連想される事項を樹状に展開していくというものです。通常頭の中では似たような活動を行っているのですが、脳の能力の制限から、頭の中では直近に考えた一部のことだけを明確に頭の中におき、他の以前に考えた部分は霧の中にあるような状況で作業をしています。
マインドマップでは、以前に考えた部分を含め、それを図にして視覚的に示し、それまでの連想の構造を可視化し、さらにその図を見ながらその図に記述されている情報・概念やその構造全体に触発されながら、つまり隣接可能性を活用して、関連する他の情報やアイデアを自分の頭に蓄積された情報に基づき引き出すものです。そして、そのマインドマップを更新・拡大していくものです。
-マインドマップの活用法
・個人の作業(リアルタイム)
このマインドマップを利用して、強制的に連想を生み出す活動は、まず個人という単位でいつでもどこでも、紙とペン、またマインドマップのスマホやPCのツールがありますので、その場で簡単に行うことができます。仕事や私生活上で直面した困ったこと、また関心を持つ社会課題などについて、その原因や解決法を、このマインドマップで広く連想をしてみるなどにより、問題・課題の原因や影響を広く捉え、またその解決策を広い視野から見つけることができます。
次回もこの議論を続けたいと思います。
(浪江一公)