『価値づくり』の研究開発マネジメント 第351回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(198): KETICモデル-思考(140)
「発想のフレームワーク(75):隣接可能性とは(3):隣接可能性促進法」
(2025年3月3日)
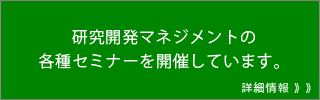 |
今回も前回に引き続き、隣接可能性を考えていきたいと思いますが、今回から複数回にわたり隣接可能性の促進法について議論をしていきたいと思います。
●隣接可能性のイノベーション創出における位置づけの確認
前回はスプレッディング・アクティベーションという言葉を紹介しました。イノベーションのメカニズムは、2つの別のニューロンがこのスプレディング・アクティベーションで同時に発火することでスパークが起こるもの、と考えることができます。したがって、イノベーションを促進するには、スプレディング・アクティベーションが頻繁に起こるようにすれば良いということになります。それでは、そのためには何をしたら良いのでしょうか?そしてその中で、隣接可能性はどのような役割を担うのでしょうか?
●隣接可能性:脳内のネットワークを拡大する一つの重要要素スプレディング・アクティベーションが頻繁に起こるようにするには、脳内のネットワークを拡大することであると思います。脳内のネットワークを拡大するには、以下の方法があると思います。
〇既存のニューロン間のシナプスによるつながりを強化する
将来イノベーションのためのスパークを起こすことになる別のニューロンに蓄積された2つの情報のつながりを、シナプスで強化する必要があります。そのためには;
-2つのニューロンをつなげる
-そのつながりを常に強化する
が必要となります。
〇ニューロンに蓄積されている情報を増やす
さらに、将来イノベーションのためのスパークを起こすことになる情報を、新に多数増やすことも重要です。そのためには;
-脳にとって全く新しい情報を付加する
-ニューロンに蓄積済の情報から情報を拡大する
の2つの方法があります。
この一番最後の「ニューロンに蓄積済の情報から情報を拡大する」に向けて、単に脳の中に自然に備わっている能力だけでなく、意図的に隣接可能性を使って情報を拡大することができると思います。
●意図的に隣接可能性を促進する方法
意図的に隣接可能性による連想を促す方法として、大きくは以下の4つがあるように思えます。
〇既存のニューロンに蓄積された個別の情報を出発点に連想を促す
まずは、脳内に蓄積された個別の情報から連想を促すという基本形です。
〇既存のニューロンに蓄積された複数の個別情報から、連想の出発点となる情報・アイデアをインテグレートしそれを可視化し、そこから連想を促す
上の変形ですが、既存の複数の個別情報から新な情報やアイデアを創出し、そこを出発点に連想を促す方法です。
〇連想のパターンを明らかにして設定し、その連想パターンに則り連想をする
連想には複数のパターンがありそうです。そのパターンに則って連想をしてみることは、有効です。
〇複数脳、時間差脳を活用する
一人の脳ではなく、複数人の脳を使って連想をしてみる。また一人の脳にしてもその時点の脳ではなく、時間をおいて別の環境にある時の脳を使って連想をする。といった方法もあるように思えます。
次回から上の意図的に隣接可能性を促進する方法について、順番にもう少し具体的に考えていきたいと思います。
(浪江一公)